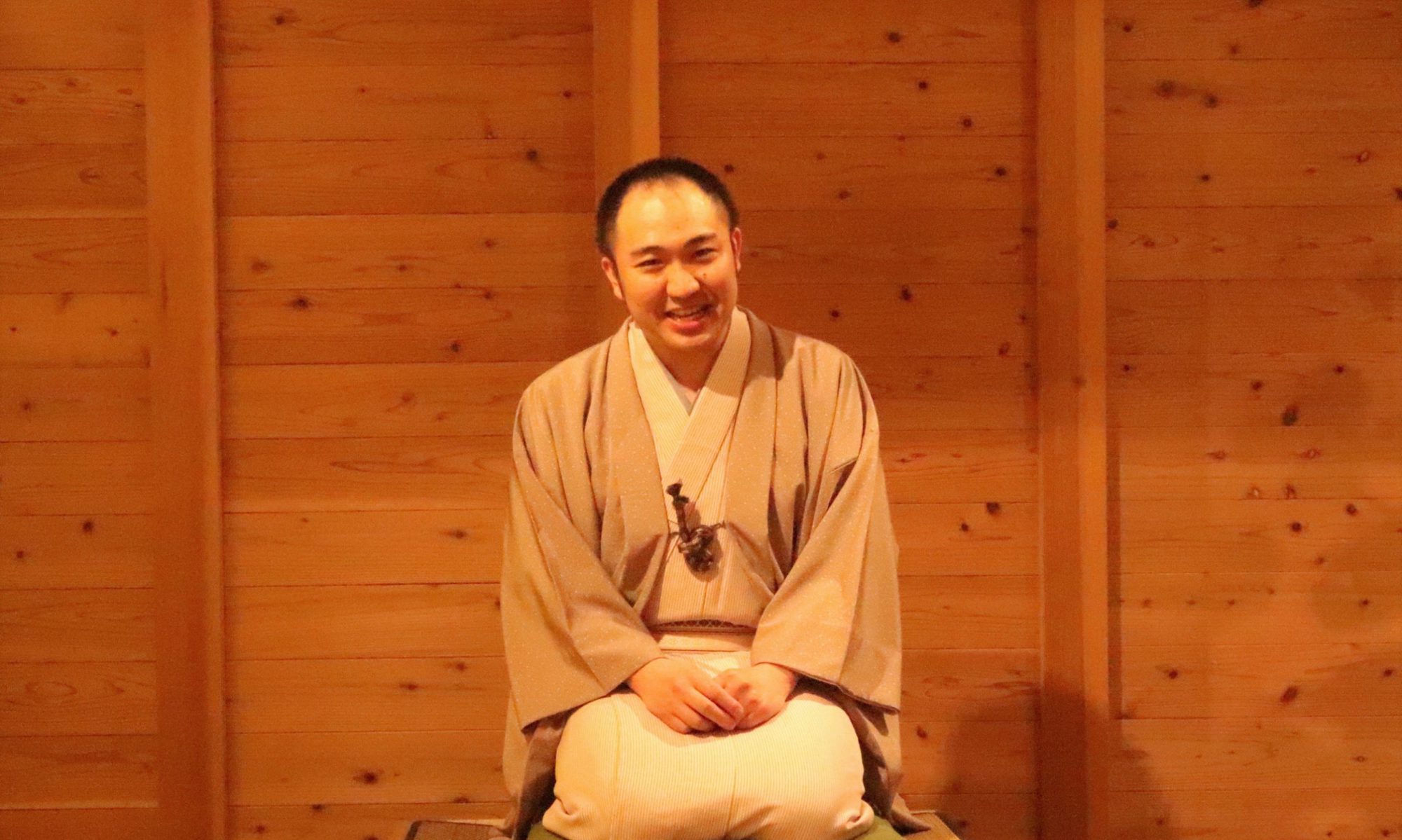◆2018年10月 いちらくご第6回のご案内です。(メルマガ)
今回は橘家圓太郎師匠を助演にお迎えしての会となります。圓太郎師匠と言えば、にっかん飛切落語会での大賞受賞者のお一人。
1978年から2007年まで毎年開催された二つ目の登竜門 「にっかん飛切落語会」。当時はその審査の厳しさから、30年の歴史の中で大賞が出たのはたったの2回。受賞されたのは柳家三三師匠と橘家圓太郎師匠のお二人だけなんです。 そんな師匠の落語を連雀亭でご覧頂ける貴重な機会です!
◆2018年10月8日 初めてこのサゲを演ったのは、二つ目になる直前。末広亭での師匠市馬と三三兄さんの二人会でした。三三兄さんから「いいサゲだなぁ」と褒められ嬉しかったなぁ(^人^) (旧Twitter)
◆2019年6月14日 披露目の支度・其之壱を終えて
披露目の支度・其之弐では、アタシの新しい芸名を発表することになっているんですが・・・
三三兄がとっさに、「今日のアンケートに名前の予想を書いて、其之弐のチケットを買って当日会場に足を運んで、名前が当たったら、手ぬぐいをプレゼントします」と仰って下さいましたが・・・。 残念ながら当たった方はいませんでした。 ちなみに兄さんは、4回で当てました。さすが兄ぃ。。。
圓太郎師匠は、「オレは聞かないからな、正式発表まで聞かないからな・・・!」 といっておられました(笑) 自分から聞いたくせに・・・(笑)。 まぁみなさま、発表まで楽しみにしていてくださいまし。
◆2019年12月12日 三三独演、卒業です。
先日は、イイノホールでの月例・三三独演へ呼んで頂きました。 数えきれないくらい、この会には出演させて頂きましたが、今回で卒業となります。 いろんな思いを込めて、『道灌』を申し上げました! 学生の頃、池袋演芸場の小三治師匠のトリを毎年見に行ってました。当時学生だったので、行く時間がいつも二つ目の頭くらいで、何故か毎回、三三兄さんが出番の時だったんです。 そこでは、兄さんが、いつも『道灌』をされてました。 当時のアタシは、「この人は、こんなにうまいのにこれしかできないのか!?」 と思ったくらい(笑)
噺家になって楽屋に入ってから、色々伺える機会があり、いろんな課題を持って『道灌』を掛けていたことを知りました。 節目節目で、兄さんが『道灌』を掛けているお姿を見てきたので、「兄さんのお客様の前で申し上げるならこれだろう」と、決めていました。(中略)
打上げで、これで卒業だね、という話になった時、兄さんが「わかんないよ(笑) 真打になっても出てもらうかもしれない」と。 確かに、兄さん、お客さんのまえでも楽屋でも一言も「卒業」とは言ってなかったもんなぁ…。 もし、また出ることになった時はよろしくお願い致します。
◆2020年8月8日 真打昇進披露興行
末廣亭での披露目2日目。 アタシの場合は師匠が落語協会会長なので、口上の師匠が他の新真打より一人少なくなってしまいます。そういう訳で、1日目は彦いち師匠、2日目は三三兄さんが口上に上がって下さいました! お二人とも司会は初めてとのこと。 有難くて、とても心に残る披露目となりました。
◆2020年12[噺のネタ]6 『やかん』(琴柳先生の講談のお稽古)
今回は『やかん』のことを。 『やかん』は噺家になって最も高座に掛けたネタです。前座の頃に柳家三三兄さんに教えて頂きました。 『やかん』は後半、講釈の件があり、それがまた聴き所でもあります。 宝井琴柳先生から『三方ヶ原軍記』を直々に教わっている三三兄さんの講釈は、言わば本物。 アタシも何とかしなくては、と三三兄さんに相談をし、琴柳先生から『三方ヶ原軍記』を教えて頂きました。
琴柳先生は保守本流。特に修羅場を読ませたら右に出る者はいないという、凄い方なんです。
先生は1回3時間のお稽古を、月に2度くらい、それを3年ほど付けて下さいました。それだけの時間と労力を講釈師でもないアタシの為に…。
講談のお稽古はまず本を作る所から始まりました。 石州半紙という紙と、たこ糸を用意して(三三兄さんが買って下さいました)、本の作り方を(三三兄さんに)教わって、本を(三三兄さんに)お借りして、それを写して(さすがに自分で)、改めて先生にお稽古をお願いしました。 最初は先生の後について「大きな声で抑揚をつけずにはっきりと読む」ことを何度も繰り返しました。(続きはブログを・QRコードからアクセスできます)
◆2021年1月[噺のネタ]7『大工調べ』(師匠・市馬からでなく…)
アタシは柳家の型。当然うちの師匠から・・でなくて三三兄さんから教えて頂きました。師匠・市馬からは二つ目になってからほとんど習ってません。 でも三三兄さんはうちの師匠から。 回りくどい師弟です(笑)
◆2021年5月[噺のネタ]12 『道具屋』(前座噺はムズカシイ)
この『道具屋』も難しい噺。 以前は圓蔵師匠と扇橋師匠が頻繁に掛けていらっしゃいましたが、お二人が亡くなってからは、寄席で中々聴けないネタになってしまいました。今ですと三三兄、それから師匠・市馬に扇治師匠、扇辰師匠辺りがたまに、というくらいでしょうか。全員研精会OBですね。
アタシは前座時分に三三兄さんに教えて頂きましたが、ウケたことは一度もありません(泣)
でも好きなんですかね、捨てきれずに引っ張り出しては痛い目を見る、を繰り返しています。
また、同じ噺であっても、うちの師匠の場合は12、3分の寄席サイズなのですが、三三兄のは35分強もあり細部も盛り沢山。伝書鳩、歳の市、葉唐辛子、天麩羅の屋台、毛抜き、元帳の件(くだり)、と言って何のことかわかる人は落語マニアです。
そういう事もあり、師匠も「『道具屋』は三三に習え」と稽古に出してくれました。
毛抜きの件は特に難しく、アタシには(ウケるウケない以前に)出来ません。 三三兄は以前、楽屋で毛を抜く稽古をずっとやりすぎて、一時期エア毛抜きが癖になっていたくらいです。
アタシは天麩羅の件が好きです。 いつかは『道具屋』を持ちネタにしたいなぁ。
◆11月16日(日)こおりやま寄席・柳家三三独演会へ出演いたします→詳細はスケジュールを