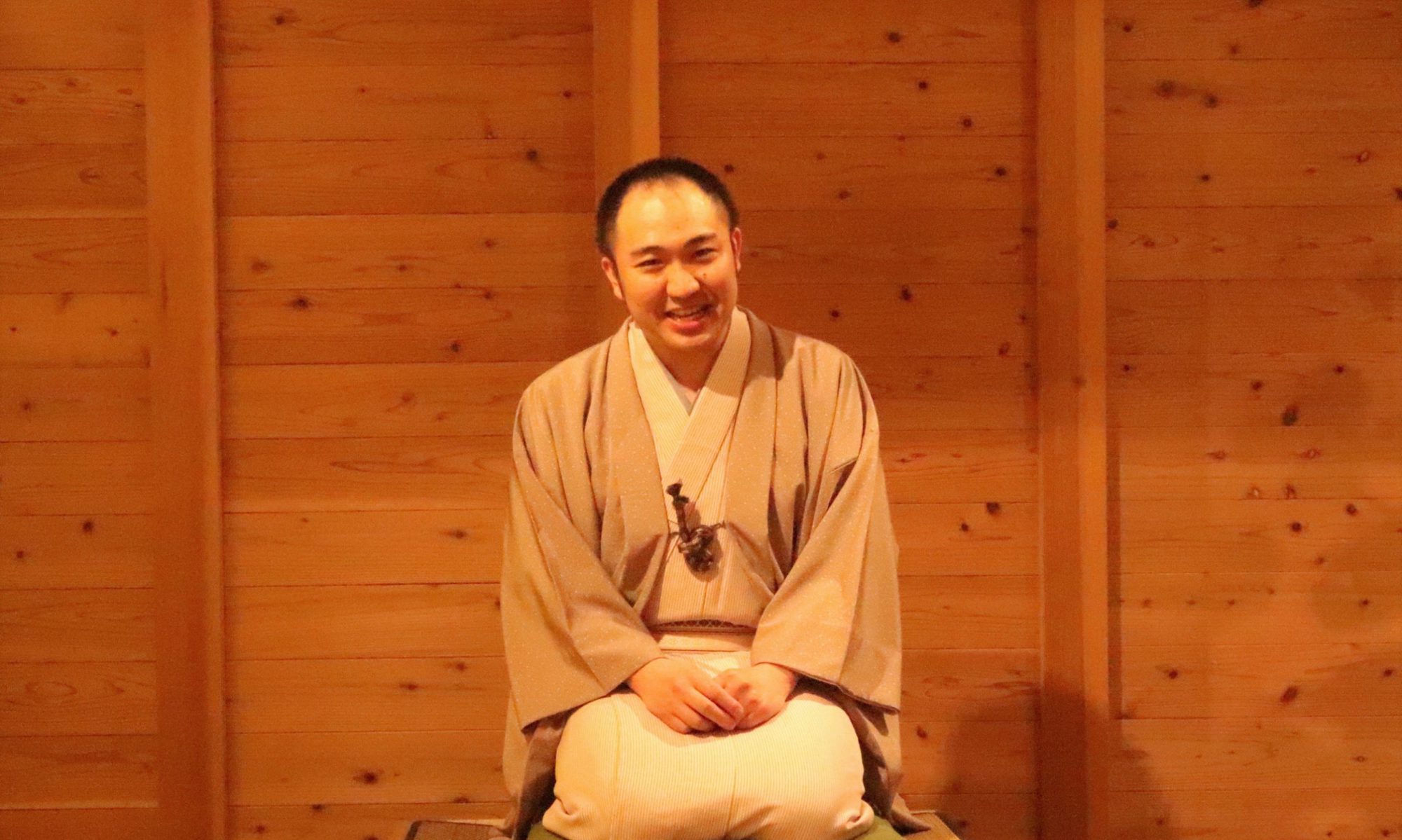先日は池袋柳勢会でした。
ご来場頂いたお客様、ありがとうございました。
今回ネタ出しの『死神』は、柳家喬太郎師匠にお稽古をつけて頂きました。
二つ目の終わり頃でした。
それまでは明るい噺をやることが多かったので、随分苦労して高座に掛けた覚えがあります。
『死神』って落語っぽくないでしょ?
それもそのはずで、原作がグリム童話。
そこで怪談寄りの変わった噺として演出するか、あくまでも落語として高座に掛けるか、によって噺の印象も違ってきます。
圓生師匠の下げでやれば、怪談寄り。
小三治師匠のくしゃみの下げなら落語としての演出となります。
(例外もあるのかもしれません)
一時期、『死神』は如何にして新しい下げを作るか、という風潮になってしまった時期がありました。
ただ下げを変えるのも良いけれど、大事なのは演出(注)であり演技である、とみんなが気がついたので、今ではあまり気にしなくなってきたのではないでしょうか。
ちなみに三遊亭兼好兄さんの下げがとてもシャレていて、後輩が生意気ですが、いいな、と思いました。
機会があれば是非。
また、『死神』には噺の穴が多過ぎる、とよく仲間内で言われます。
例えば
◯なぜ死神はこの噺の主人公に呪文を教えたのか?
◯なぜこの主人公以外には死神が見えないのか?
◯なぜ上方見物で浪費したあと、往診の依頼が来なくなったのか?
◯なぜ布団を回すことを思いついたのか?
◯なぜ最後別のロウソクにつけ替えるチャンスを与えたのか?
等々…
実はまだ他にもあります。
アタシも習った形から上記以外の穴を1つ埋めました。
いや、埋めた…というより、くすぐりをカットして穴を作らない様にしたのです。
(詳しくは「ここだけの話」でお話しすることもあるでしょう)
落語にはたいてい何らかの穴はあります。
しかし、こんなに穴がありながら人気のあるネタは珍しいのではないでしょうか。
穴があるから面白い!そう演者に思わせる魅力があるのかもしれません。
皆がそれぞれの考えで穴を埋めたり、埋めなかったり。
なので、上記の穴をどう処理しているのかいないのか。
それを気にして聴いてみるのも面白いと思いますよ。
(注)
最近は『死神』のキャラクターを変えることで差別化を図る方もチラホラ。
なかで鶴瓶師匠の『死神』は『エリザベート』の影響があると思うのですが、どうなんでしょう?
(2025.4.27 18:56 HPに投稿)
これまでの噺のネタはこちら